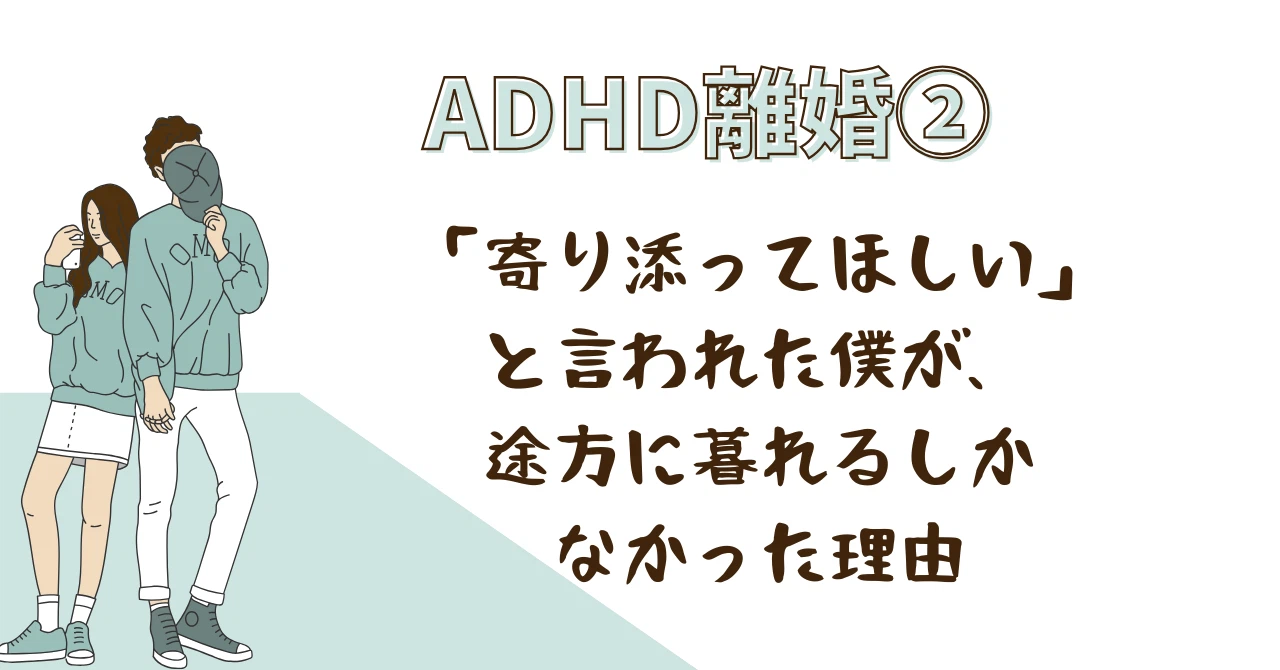
「寄り添ってほしい」と言われた僕が、
途方に暮れるしかなかった理由
【ADHD離婚②】
「わたしのことを、全然わかってくれない」
「もっと、気持ちに寄り添ってほしい」
かつてのパートナー、ミキちゃん(仮)は、涙ながらにそう訴えました。
僕は、その言葉を聞くたびに、心の中で途方に暮れていました。
「寄り添ってあげたい。でも、どうやって?『寄り添う』って、一体何をすればいいんだ?」
はじめまして、「凸凹ADHD」のデコさんです。
これは、僕の後悔の記録であり、今まさに同じ悩みを抱えているかもしれない、あなたへの手紙です。シリーズ第二弾のテーマは、僕ら発達障害の特性を持つ人間がしばしば直面する、「相手の感情を理解し、共感すること」の難しさについてです。
「どうすればいいか、具体的に教えて」が通用しない世界
ミキちゃんが感情的になっている時、僕はいつもパニックでした。
彼女を助けたい。この状況をなんとかしたい。その思いから、僕は必死に「解決策」を探そうとしました。
「何が問題なの?」「どうすれば解決する?」「具体的に言ってくれないと、分からないよ」
しかし、僕がそう言えば言うほど、ミキちゃんはさらに深く傷つき、絶望していきました。
「そういうことじゃない!」「なんで分からないの!?」「それくらい自分で考えて!」
当時の僕には、本当に分かりませんでした。
彼女が求めていたのは、具体的な「問題解決」ではなく、ただ「気持ちを分かってもらう」という、目に見えない共感だったのです。
しかし、僕の脳は、そのあまりにも抽象的な要求を、どう処理していいか分かりませんでした。
僕の脳は「他人の感情」をリアルに感じることが苦手
なぜ、僕はミキちゃんの気持ちに寄り添えなかったのか。
ADHDの診断を受けた後、さらに自分を深く見つめる中で、僕は気づきました。この「共感の苦手さ」は、ADHDだけでなく、ASD(自閉スペクトラム症)の特性にも当てはまることを。そして、僕自身もその傾向を持っているのだと。
僕の脳は、どうやら他人の感情や、その場の空気を、自分自身の感覚としてリアルに感じ取ることが苦手らしいのです。
ミキちゃんの悲しそうな表情、声の震え、ため息…。
それらが「つらい」という感情のサインであることは、頭では理解できます。しかし、その感情が「自分の中で同じように再現される」という、いわゆる「共感」のプロセスが、僕の脳内ではうまく機能しなかったのです。
僕にとって、彼女の感情は、まるでガラス一枚を隔てた向こう側の出来事のようでした。嵐が起きているのは見える。でも、風の強さも、雨の冷たさも、肌で感じることができない。だから、僕はただ冷静に「どうすれば嵐が止むか」という、見当違いな「対策」ばかりを考えてしまっていたのです。
すれ違いを生んだ「事実」と「感情」の記憶の差
この「共感」の苦手さは、「記憶」の問題とも複雑に絡み合っていました。
僕は、「今週末、ハイキングに行く」といった、具体的な「事実情報(ファクト)」を覚えるのは比較的、得意でした。
しかし、ミキちゃんが「この前、〇〇が悲しかった」と話した、感情に紐づく「エピソード」は、僕の頭から抜け落ちやすかった。
彼女からすれば、「ハイキングの予定は覚えているのに、私が悲しんだことは忘れるなんて。結局、私の気持ちなんてどうでもいいのね」と感じたことでしょう。
僕の脳の特性が、「愛情がないから、気持ちを理解しようとしないし、覚えてもいない、冷たい人間だ」という、最悪の誤解を生んでしまったのです。
もし、あの頃に戻れるなら
あの頃の僕は、この脳の仕組みを言葉にできず、ただ「具体的に言ってくれ」と繰り返し、ミキちゃんを失望させることしかできませんでした。
今になって思えば、あの頃の僕らは、お互いに「ないものねだり」をしていたのかもしれません。
ミキちゃんは、僕に「感情の察知」という、僕が持っていない能力を求めた。僕は、彼女に「感情の言語化」という、彼女が苦手としていた能力を求めた。
どちらが悪いわけでもない。
ただ、お互いの「できないこと」を、必死に要求し合い、そして叶えられないことにお互いが傷つき、疲れ果ててしまった。それだけだったのかもしれません。
もし、ADHDとASDの特性を理解した今の僕が、あの頃に戻れるなら。
僕は、一方的に何かを求めるのではなく、まず自分の不完全さを認め、自分たちが置かれている状況を伝えるでしょう。
ごめん。僕は、ミキちゃんの『つらい』という気持ちを、同じように感じることが苦手みたいなんだ。これは、愛していないからじゃない。僕の脳が、感情を読み取ることが苦手な特性を持っているだけなんだ。
だから、ミキちゃんの感情を『嬉しい』『悲しい』『腹が立つ』といった、具体的な“言葉”にして教えてほしい。その代わり、僕は、言葉にしてくれた感情を、決して忘れないように、ノートに書き留めていく。そして忘れないように毎日見返すようにするよと。
そうやって、お互いの苦手なことを補い合い、二人が気持ちよく暮らせるようにしていけないだろうかと。
この問いかけが、あの頃の僕にできていたなら。僕らは、「わかってくれない人」「ヒステリックな人」と傷つけ合うのではなく、ただ「共感が苦手な僕」と「それを悲しく思うミキちゃん」として、もう一度向き合えたのかもしれないと思います。
【ADHD離婚シリーズ】
①一つのことにしか意識を向けられない不器用な真実
②「寄り添ってほしい」と言われた僕が、途方に暮れるしかなかった理由
③僕の「得意なこと」は、なぜ努力として認められなかったのか。
④「それくらい自分で考えて」が、僕には一番難しい呪文だった。
⑤なぜ僕は「名もなき家事」が全く見えなかったのか。
⑥なぜ僕らは、「二人でいる時」が一番孤独だったのか。
⑦妻のイライラから「逃げる」以外の選択肢を、なぜ持てなかったのか。
⑧なぜ僕は、妻からの「パシリありがとう」に喜んでしまったのか。