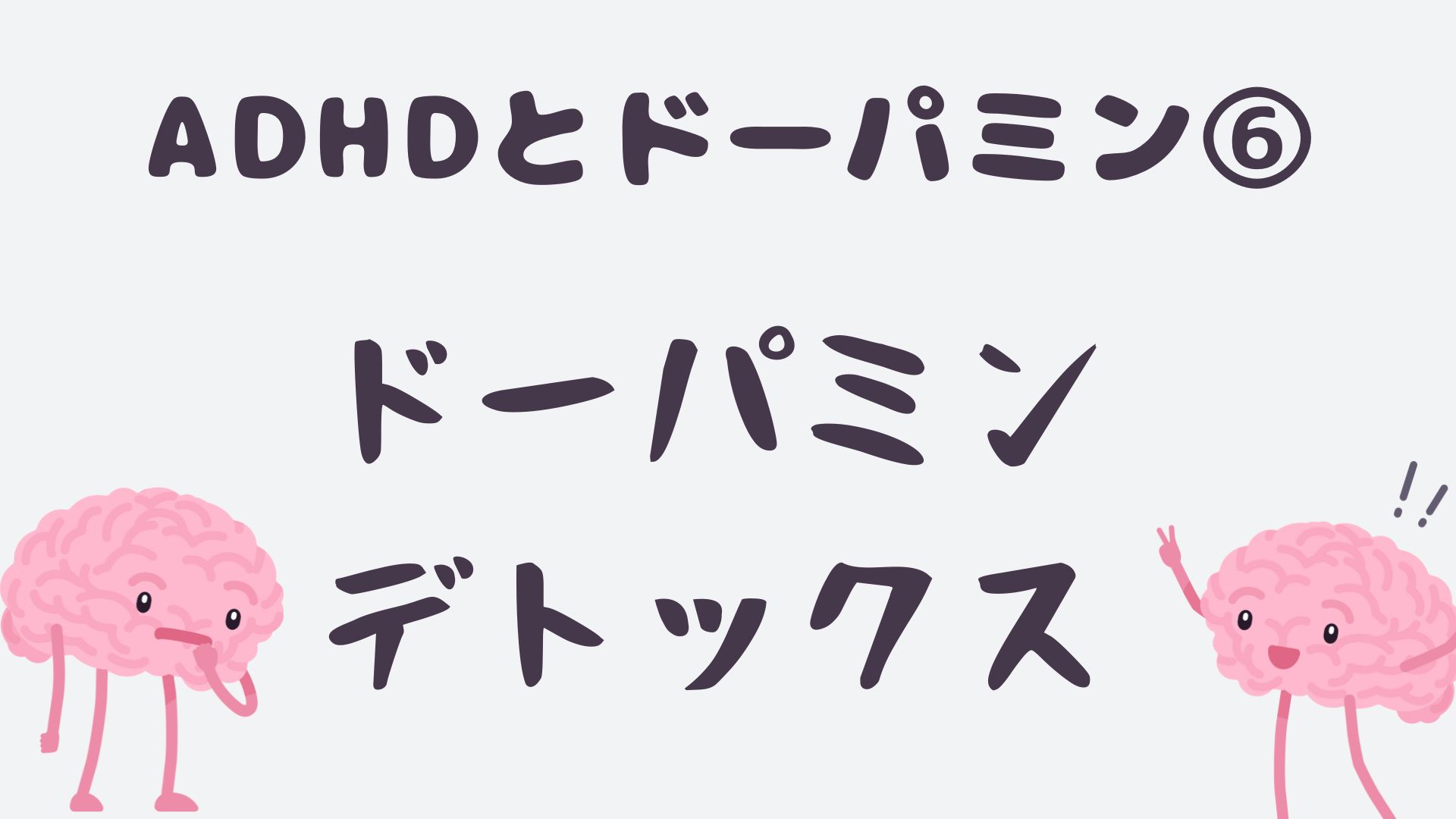
ドーパミンデトックス
【ADHDとドーパミン⑥】
「あと1本だけ…」
「もうちょっとだけ…」
気づけば、スマホの画面を眺めて数時間。やるべきことは山積みのはずなのに、なぜかショート動画をスワイプする指が止まらない。そんな経験はありませんか?
はじめまして、「凸凹ADHD」のデコさんです。前回の記事「ドーパミンと休息」では、「良いドーパミン」活動ですら、やりすぎると僕らを疲れさせてしまうこと、そして刺激を「引く」、つまり休息がいかに大切かをお話ししました。
今日は、ドーパミンのさらに厄介な側面、「中毒(依存)」について掘り下げていきます。なぜ僕らは特定の行動(SNS、ゲーム、ジャンクフード…)にハマりやすく、そこから抜け出すのが難しいのか。その脳の仕組みを知り、ドーパミンという強力なエンジンと健全に付き合っていくための戦略を探っていきましょう。
そもそもドーパミンは、僕らが目標を追いかけたり、新しいことに挑戦したりするための「行動のエンジン」として、進化の過程で備わった大切な神経伝達物質です。危険を冒して獲物を追いかけたり、新しい土地を探したり…そんな「結果が予測できない挑戦」を促すことで、人類の生存を支えてきました。ところが、現代社会はこのドーパミンシステムにとって、あまりにも刺激が多すぎる環境です。
-
スマホの通知
-
次から次へと流れてくるショート動画
-
手軽に食べられるジャンクフード
-
クリア報酬が用意されたゲーム
世界中の優秀なエンジニアたちが、僕らをできるだけ長く自分のサービスに引き止めるために、ドーパミンの仕組みを巧みに利用しています。その結果、僕らの脳は、常に「強い刺激」にさらされ続けることになります。
すると、脳はどうなるか? まるで薬物依存と同じように、「ドーパミン耐性」ができてしまうんです。つまり、ドーパミンが出ても、以前ほど効きにくくなる状態。だから、同じ「快感」を得るためには、もっと強い刺激、もっと多くの量を求めるようになってしまう。「もっと欲しい!」という衝動に、脳が乗っ取られていくような感覚です。
ドーパミンは、僕らに素晴らしい行動力や集中力を与えてくれる一方で、使い方を間違えると、僕らの人生を蝕むほどの力も持っている。だからこそ、その仕組みを理解し、うまく付き合っていく必要があるんです。
では、どうすればいいのでしょうか? 鍵は、まず過剰な刺激に慣れてしまった脳を一度リセットする「ドーパミンデトックス」が効果が高いようです。
自分の意志力だけに頼るのではなく、誘惑(ドーパミン源)との間に物理的・時間的な「壁」を作って、一定期間、衝動的にアクセスするのを防ぐ工夫です。
物理的な壁の例としては、ハマっているアプリ・ゲームがあればスパッと削除する。僕の場合はダダサバイバーというゲームでした。本当に何も得るものは無いけど、めっちゃドーパミンがでるゲームでした。年末年始にさんざんハマってしまい、これは行けないと思い、スパッと削除しました。
あと、お菓子を家に置かない。僕はあればついつい見境なく最後まで食べてしまうので、家にお菓子はおきません。例えば、 寝室にいる間は、スマホは手の届くところおかない。SNSは1日30分までと決める(タイマーを使う)などなど。僕はNoteを読む時間も、今から15分間読むだったりその時に合わせて時間を決めて読んでいます。
いきなり全てを断つのが難しければ、「朝だけ」「寝る前だけ」など、時間帯を決めて刺激から離れることから始めましょう。(前回の「休息」の話にも通じますね!)
また、感情の客観視をするのも効果的なようです。「あ、今スマホ触りたい衝動が来てるな」「甘いもの食べたいって脳が言ってるな」と、自分の欲求を第三者のように感じて心の中でつぶやいてみます。これだけで衝動との間に距離ができ冷静になれます。衝動のピークは意外と短い(10分程度)ことが多いらしいのです。
前回の記事でも紹介しまししたが、スマホを持たずに散歩する、カフェで注文を待つ間ぼーっとする。意図的に「何もしない時間」を作ることで、刺激過多になった脳がリセットされ、ドーパミンの感受性が正常に戻りやすくなります。
最後に、依存からの回復を持続させるために、とても大切なことがあります。それは「正直さ」です。依存行動をしている時、僕らはつい嘘をついてしまうことがあります。自分に対しても、周りの人に対しても。「大したことない」「コントロールできている」と。アルコールに依存していたころは、酔っぱらってバカみたいなことをしてしまった事をまるで武勇伝でも語るように笑いのネタとして話していました。そんな風に、現実に向き合わずにいることが、依存を隠し、問題を悪化させる原因になるのだと思います。
自分の弱さや失敗、依存行動について、信頼できる人に正直に話すこと。それはとても勇気がいることですが、罪悪感や孤独感から解放され、本当の意味での回復につながる大切な一歩です。
そして、思い出してください。僕らの幸福は、ドーパミン(やる気・達成感)だけで成り立っているわけではありません。セロトニン的な幸福(心身の健康、穏やかさ)と、オキシトシン的な幸福(人との繋がり、安心感)という土台があってこそ、ドーパミン的な幸福も健全に輝きます。
ドーパミンとうまくやること、良くも悪くもドーパミンに影響を受けやすいのがADHDです。ドーパミンとのうまい付き合い方を学んで人生を幸せに、充実させていきましょう。
【ADHDとドーパミン】シリーズの最初の記事はこちら
【ADHDとドーパミン】シリーズはこちら
①ADHDの脳の「支配者」
②短期的な快楽に飲み込まれる
③運動という名の「脳のお薬」
④「社会的ドーパミン」を得よう!
⑤ドーパミンと休息
⑥ドーパミンデトックス
⑦ドーパミン中毒と隠れた原因
⑧最終的なドーパミンとの付き合い方
【ADHD離婚からの再生】シリーズ
※過去のシリーズですがドーパミンに深く関係しています。
①ADHDの禁酒と禁煙
②禁酒後の新しい世界
③「動」と「静」で脳を整える
④運動は「最高の処方箋」
⑤習慣化できますか?
⑥「失敗だらけの過去」の意味